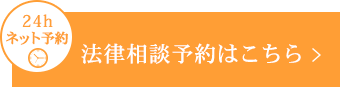2025.9.13 相続・遺言
相続が発生した場合に、被相続人の住所や財産の状況などを知る方法
① 被相続人の住民票の住所を知る方法
- 除票(住民票の除票)
被相続人が亡くなった後、役所では住民票が「除票」となります。これを市区町村役場で請求できます。- 請求できるのは相続人などの「正当な利害関係人」に限られます。
- 除票には最後の住所地が記載されています。
- 戸籍の附票
被相続人の戸籍謄本を取ると、その「附票」から過去の住所履歴を確認できます。- 相続財産調査の際に、どの自治体で不動産を持っている可能性があるか推定する手掛かりになります。
② 不動産の所有の有無と所在地を知る方法
- 法務局での不動産登記事項証明書の取得
不動産は登記されていますので、所在地が分かれば、管轄の法務局で登記事項証明書(登記簿謄本)を請求できます。 - 名寄帳・固定資産課税台帳の閲覧
不動産所在地の市区町村役場で「名寄帳」や「固定資産課税台帳」を請求できます。- 相続人であることを証明(戸籍など)すれば、相続人が請求可能です。
- 所有不動産をまとめて確認できる場合があります。
- 登記情報提供サービス
オンラインでも住所や地番が分かれば、不動産登記事項の情報を有料で取得できます。
③ 名寄せ(資産調査)の方法
「名寄せ」とは、被相続人名義の財産を一括して把握する調査を指します。
- 不動産に関して
→ 各市区町村役場の「名寄帳」で名寄せ可能です。
→ 被相続人名義の不動産がその自治体にあるかどうか確認できます。 - 金融資産に関して
→ 相続人が金融機関に対して「残高証明書」を請求できます。
→ 口座がどこにあるか不明な場合は、被相続人の通帳・郵便物・確定申告書などから手掛かりを探します。
上記を要約しますと、下記のとおりとなります。
- 住所は「住民票の除票」「戸籍附票」で確認。
- 不動産は「登記事項証明書」「固定資産課税台帳」「名寄帳」で調査。
- 名寄せは主に市町村役場(不動産)、金融機関(預金)ごとに行う。